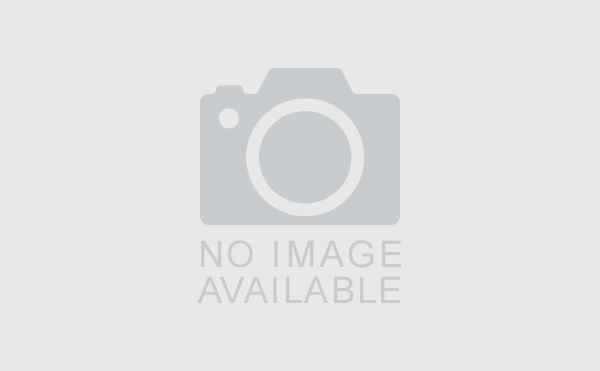グローバル企業の定義
| さてまずはさっそく、第一回目のテーマとしてグローバル企業とは?です。 日本はいまや、海外との取り引き無くして成り立たないのは誰も異存はないでしょう。 その中で国内でグローバル企業が育っているのか?探ってみましょう。 その為にはまず、グローバル企業の定義をしなければなりません。 最新の経営理論では以下の通り、定義されます。 グローバル企業の定義) 世界で通用する強みがあり、それを活かして世界中で満遍なくビジネスができている商品力、技術力、人材、ブランドなどの海外で成功する強みのことを経営学では FSA(Firm Specific Advantage) 企業固有の優位性と言う。 米インディアナ大学の重鎮 アラン・ラグマン ジャーナル・インターナショナル・ビジネススタディーズに発表した論文2001年時点米フォーチュン誌世界主要500社(世界の海外直接投資の9割はこの500社による)中、売上データの取れる365社(主要な巨大多国籍企業と呼べる)を抽出。 世界市場を北米、欧州、アジア太平洋の3地域に分け、365社の売上シェアを精査、集計した。 本社の地域をホーム地域として5割以下、他の2地域の売上がそれぞれ2割以上あれば真のグローバル企業と呼べると定義した。 …さて、そこでこの定義に当てはまるグローバル企業は?日本国内企業は? 次回以降でそこを探っていきます。 2021年7月3日 →結果 ①ホーム地域への強い依存 320社が5割以上をホームから売上げている。残りは45社しかない ②真のグローバル企業は9社だけ 45社のうちホーム外の2地域の両方からそれぞれ2割以上の売上シェアを実現できている(つまり言い換えると世界の主要3地域で満遍なくビジネスしている)企業は以下9社しかない IBM、インテル、フィリップス、ノキア、コカコーラ、フレクトロニクス、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン、ソニー、キヤノン →マクドナルド、トヨタ、ホンダ(欧州では苦戦)はこの中には無い この事実は衝撃だった→それまでは学者は自国以外でビジネスをする=グローバルだったから。 あくまでもこの結果は売上なので、本当は利益も見たいし、ホーム地域の経済規模の大きさも影響、コンシューマー向けかBtoB企業かでも違うが…これら事実から少なくとも2004年以降はグローバル化の概念は盲目的に単純化させてはならないとされている。 という事で所謂、世界のグローバル企業の実情が判明したところで、いよいよ次回は日本のグローバル企業を探ります。 2021年7月5日 さて世界のグローバル企業の実情が分かったところで日本は? データが少し前のものになりますが、2003年時点500社のうち64社が日本企業、ホーム売上が半分を超える企業は57社(81%)。 そこで定義に従うと真のグローバル企業はソニー、キャノン マツダしかないと言う結果になります。 更に2014年に真にグローバルな企業は?と言うと45社しかありません。 そのうち36社がホームで半分以上。 条件を満たしたのはキヤノンとマツダの二社のみ。 トヨタは欧州では9.9%、ホンダ5.3%日産15% (最新ではコロナもあり、少し変わっているかもしれません。) ホームで強みを発揮する企業をRSA(Regionnal Specific Advantage)と呼びますが、そもそもまんべんなく世界3地域で成功している企業は世界中見渡しても殆ど存在しません。 ↓ 良く言われる様な「アジアや北米ではこれだけ儲かっているのにおかしい」などと言う視点自体見直す必要があると言う事ですね。 ※参考引用:世界標準の経営理論 入山章栄著 |